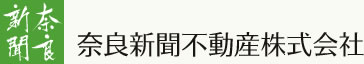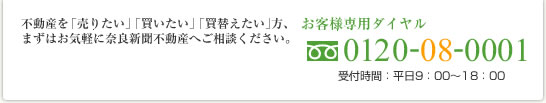さ
-
再開発等促進区
再開発等促進区
- 【読み】
- さいかいはつとうそくしんく
- 【意味】
再開発等促進区とは、地区計画の区域で、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域として、都市計画に定めることができるものです。
再開発等促進区を定めることのできる区域の条件は下記のとおりです。
①現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること
②土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置および規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること
③当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること
④用途地域が定められている土地の区域であること
-
債権者代位権
債権者代位権
- 【読み】
- さいけんしゃだいいけん
- 【意味】
債権者代位権とは、債務者が無資力となったため債権者に債権保全の必要性が生じたとき、債務者が他の者に対して有している権利を債務者に代わって行使する権利です。
これによって債務者が責任財産(強制執行の対象となる財産)の減少を防ぐことができます。
例えば
Aさん(債務者)がBさん(債権者)から100万円を借りている場合において、Aさん(債務者)が無資力となったとします。もしも、Aさん(債務者)がCさんに対して100万円貸していたなら、Bさん(債権者)はAさん(債務者)に代わってその権利を行使することができます。
-
債権譲渡
債権譲渡
- 【読み】
- さいけんじょうと
- 【意味】
債権譲渡とは、債権をその性質を変えないまま(同一性を保って)他人に譲ることです。債権は財産の1つとして取引の対象となり、他人に譲渡することができます。このとき債務者の同意を得る必要はなく、譲渡人と譲受人との合意のみで自由に譲渡することができるのが原則です。
債権譲渡がなされたときに、譲受人が債権行使を債務者に行うためには、譲渡について、譲渡人からの通知または債務者からの承諾が必要になります。
-
催告の抗弁権
催告の抗弁権
- 【読み】
- さいこくのこうべんけん
- 【意味】
債権者が、保証人にいきなり債務の履行を請求したとき、保証人は、「まず主債務者に請求してくれ」と言うことができる権利です。
-
採草放牧地
採草放牧地
- 【読み】
- さいそうほうぼくち
- 【意味】
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作、または養畜の事業のための採草、または家畜の放牧の目的に供される土地のことをいいます。
つまり
実際に採草放牧地として利用されている土地は、地目などに関係なく、採草放牧地であるということになります。
-
再代襲
再代襲
- 【読み】
- さいだいしゅう
- 【意味】
再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者の子が代わりに相続する制度です。
この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません。
-
再調達原価
再調達原価
- 【読み】
- さいちょうたつげんか
- 【意味】
対象不動産を、価格時点において再調達することを想定した場合に必要とされる、適正な原価の総額をいいます。
-
債務不履行
債務不履行
- 【読み】
- さいむふりこう
- 【意味】
債務不履行とは、債務者が自分に責任のある理由(帰責自由)で、債務の本旨に従った履行をしないことです。「債務の本旨に従った履行」とは、契約に定められた内容に従った履行のことです。
債務者の債務不履行に対して債権者は、損害賠償請求や契約の解除をすることができます。
債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類があります。
例えば建物売買契約で、約束の期日までに買主が売買代金を用意できなかった場合などが債務不履行にあたります。
-
最有効利用
最有効利用
- 【読み】
- さいゆうこうりよう
- 【意味】
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成されます。これを最有効使用の原則といいます。
-
詐害行為取消権
詐害行為取消権
- 【読み】
- さがいこういとりけしけん
- 【意味】
詐害行為取消権とは、債務者が債権者に弁済できなくなることを承知で自己の財産を処分した場合に、債権者がその処分行為の取消しを裁判所に求める権利をいいます。
詐害行為取消権は、取消しをする債権者自身だけではなく、すべての債権者の債権回収を図ることを目的として、債務者の責任財産(強制執行の対象となる財産)を確保する制度です。
-
詐欺
詐欺
- 【読み】
- さぎ
- 【意味】
詐欺とは、相手方を騙して意思表示をさせることです。
相手方の詐欺によって意思表示をした者は、その意思表示を取り消すことができます。
ただし、詐欺による意思表示の取消しは、その取消し前に現れた善意の第三者に対抗することができません。
-
先取特権
先取特権
- 【読み】
- さきどりとっけん
- 【意味】
先取特権とは、法律で定める一定の債権を有する者が、債務者の一般財産または特定の財産について、他の債権者より優先して弁済を受けることができる担保物権です。
先取特権には、「一般の先取特権」、「動産の先取特権」、「不動産の先取特権」があります。
例えば
借家人が家賃を滞納した場合、家主には借家人から家賃を回収するための先取特権があります。家主は借家人の動産を競売して、その売却代金を滞納家賃に充てることができます。
-
錯誤
錯誤
- 【読み】
- さくご
- 【意味】
錯誤とは、勘違いにより本心とは異なる意思表示をすることをいいます。契約の重要な部分について勘違い(要素の錯誤)をして契約を締結した場合、その契約は原則として無効です。
虚偽表示と違って、錯誤の場合は無効を善意の第三者にも主張できます。ただし、意思表示をした者が、ちょっと注意をすれば勘違いを防げた(重大な過失があった)
場合は、契約を無効にすることはできません。
例えば2つマンションを持っていて、そのうちの1つを売ったら、売りたい方のマンションでなかった、という場合。契約の重要な部分に勘違いがあったため、契約は無効になります。ただし、売主に重大な過失があった場合は、契約は無効であるといえません。
-
詐術
詐術
- 【読み】
- さじゅつ
- 【意味】
詐術とは、制限行為能力者が自ら行為能力者であると偽ることをいいます。
例えば未成年者なのに、年齢を偽って成年者だとだました場合などが、詐術にあてはまります。
-
山麓部
山麓部
- 【読み】
- さんろくぶ
- 【意味】
山麓部とは、山の裾野に広がった部分をいい、水の便や水はけも良いので、宅地に適しているといえます。
しかし、山麓部の利用において、崖下、急傾斜地は避けるべきです。また、過去の土石流、地滑り、土砂崩落による堆積でできた地形は、水はけは良いですが、崩壊の危険があり、特に谷の出口にあたる部分は危険です。
さらに土石流(火山麓では火砕流)は、年月を経て繰り返すこともあるので、住宅地としての利用は避けるべきです。
し
-
市街化区域
市街化区域
- 【読み】
- しがいかくいき
- 【意味】
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に、市街化を図るべき区域をいいます。
つまり、市街化区域とは、街づくりを進めていく地域のことです。
-
市街化調整区域
市街化調整区域
- 【読み】
- しがいかちょうせいくいき
- 【意味】
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。
つまり
市街化調整区域とは、街づくりを抑えて、自然を残す地域です。
市街化区域 ①すでに市街地を形成している区域
②おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
-
市街地開発事業
市街地開発事業
- 【読み】
- しがいちかいはつじぎょう
- 【意味】
市街地開発事業とは、土地区画整理事業(土地の区画変更や造成工事をして、道路や公園などを整備すること)や新住宅市街地開発事業(○○ニュータウンなどの造成)などを総称していいます。
市街地開発事業に関する都市計画は、原則として、都道府県によって、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内に定められます。
-
敷金
敷金
- 【読み】
- しききん
- 【意味】
アパートやマンションを借りるとき、賃借人(借主)から賃貸人(貸主)に対して、敷金として家賃の何か月分かを支払うのが普通です。
この敷金は、賃借人が賃料を支払えなくなった場合や、部屋を傷つけて修復にお金がかかる場合などに備えて、賃借人から賃貸人に支払われるものです。
賃貸借終了後、家屋の明け渡しが完了したら、未払賃料や修復代などを差し引いた残額は、賃借人に返されます。
ただし、賃借人は、敷金の返還と引換えに家屋を明け渡すという同時履行の抗弁権を主張することはできません(家屋の明け渡しが先です)。
-
事業用定期借地権
事業用定期借地権
- 【読み】
- じぎょうようていきしゃくちけん
- 【意味】
事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物(マンションなど居住用を除く、例えばコンビニエンスストアなど)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上50年未満とした借地権のことをいいます。
この契約は、公正証書によってしなければなりません。
借地権の存続期間・契約の更新・建物再築による期間延長・建物買取請求権に関する規定は適用されません。
期間が満了すると借地権は消滅します。借地人は、建物を取り壊し、土地を更地に戻して、地主に返還しなければなりません。
-
事後届出制
事後届出制
- 【読み】
- じごとどけでせい
- 【意味】
事後届出制とは、一定面積以上の土地において、土地売買などの契約をした場合には、その土地の利用目的や対価を、都道府県知事(指定都市の長)に届け出なければならない、という制度です。
届出は、契約によって土地に関する権利を取得する者または権利の設定を受けることとなる者(権利取得者)が行います。
<事後届出が必要な契約と必要でない契約>
必要な契約 必要でない契約 売買契約、売買予約、停止条件付売買契約、交換契約 贈与契約 売買予約完結権の譲渡、所有権移転請求権の譲渡、買戻権の譲渡 売買予約完結権の行使、所有権移転請求権の行使、買戻権の行使
権利金の授受のある賃貸借契約や地上権設定契約、譲渡担保契約 権利金の授受のない賃貸借契約や地上権設定契約、地役権設定契約、抵当権設定契約、質権設定契約
代物弁済契約、信託財産の売却契約
信託の引受け
-
事情補正
事情補正
- 【読み】
- じじょうほせい
- 【意味】
取引事例が特殊な事情(売り急ぎなど)を含み、これが取引価格に影響を及ぼしているときに、その価格を適切に補正することをいいます。
-
自然堤防
自然堤防
- 【読み】
- しぜんていぼう
- 【意味】
河川沿いの低地に洪水のときに堆積した土砂でできた微高地
-
質権
質権
- 【読み】
- しちけん
- 【意味】
質権とは、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から引渡しを受けた物を占有(留置)し、弁済がなければその目的物から優先して弁済を受けることができる担保物権です。
質権には、動産質、不動産質、権利質があります。
例えば
Aさんが土地を担保にしてBさんからお金を借りた場合、お金を返すまでBさんはAさんの土地を留置することができます。
そしてお金を返すことができない場合は、Bさんは土地を競売にかけて、その売却代金を借金の返済に充てることができます。
-
指定確認検査機関
指定確認検査機関
- 【読み】
- していかくにんけんさきかん
- 【意味】
指定確認検査機関とは、建築物を建築する際に必要な建築確認、中間検査、完了検査などを行う民間の機関です。
これらの業務を行おうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けなければなりません。
-
支店
支店
- 【読み】
- してん
- 【意味】
実際に宅建業を営んでいる場合のみ、事務所となります。例えば、本店では宅建業を行っているけれど、支店では建設業のみを営んでいるときは、その支店は宅建業法上の事務所ではありません。
-
時点修正
時点修正
- 【読み】
- じてんしゅうせい
- 【意味】
取引事例に係る取引の時点が価格時点と異なる場合に、価格の変動率を求めて、取引事例の価格を価格時点の価格に修正することをいいます。
-
事務所
事務所
- 【読み】
- じむしょ
- 【意味】
宅建業を開業するには、事務所を設置しなければなりません。
宅建業法における事務所には、本店(主たる事務所)と支店(従たる事務所)があります。
本店は支店を統括し、支店に対し指揮・命令を行うところです。
-
借地権
借地権
- 【読み】
- しゃくちけん
- 【意味】
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。
建物の所有を目的としない場合、例えば、駐車場として土地を借りる場合は、借地借家法(社会的・経済的に弱い立場にある借地人や借家人を保護するために特別に制定された法律)の適用はありません。
また、一時的に土地を借りる場合、例えば、工事現場にプレハブの建物を建てるなどの目的で借りる場合も、借地借家法の適用はありません。
この借地権を有する者を借地権者または借地人といいます。そして、借地権者に土地を提供する者(地主)を借地権設定者といいます。
-
借地権の存続期間と更新
借地権の存続期間と更新
- 【読み】
- しゃくちけんのそんぞくきかんとこうしん
- 【意味】
借地権の存続期間は30年と定められています。当事者間でこれより長い期間を定めることはできますが、短い期間を定めることはできません。もしも短い期間を定めたとしても、法律によって30年とされてしまいます。
借地権が設定されて存続期間が満了した後に、借地契約を更新する場合、その期間は、1回目の更新の場合のみ20年、2回目以降は10年とされます。
つまり、借地権の存続期間は30年、20年、10年(以後はずっと10年)と更新されるたびに短くなっていきます。当事者がこれより長い期間を定めることはできますが、短くすることはできません。
-
収益還元法
収益還元法
- 【読み】
- しゅうえきかんげんほう
- 【意味】
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和をもとめることにより、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。
収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法(直接還元法)と、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を、その発生時期に応じて、現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法(DCF法)があります。
つまり
<直接還元法>
1期間の純収益を算出
↓
還元利回りで還元
↓
収益価格を求める
<DCF法>
連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を発生時期に応じて現在価値に割り引く
↓
それぞれを合計する
↓
収益価格を求める
例えば
Aマンションを貸したとすれば、いくら賃料が入るかを求めます。そして、その入るであろう賃料から逆算して、Aマンションの価格(収益価格)を求める、というような方法です。
-
住宅先行建設区
住宅先行建設区
- 【読み】
- じゅうたくせんこうけんせつく
- 【意味】
住宅先行建設区とは、住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定する区域で、新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画において、住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に定めることができます。
つまり
住宅の建設を促進するために指定される区域です。
-
集団規制
集団規制
- 【読み】
- しゅうだんきせい
- 【意味】
都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地・構造・建築設備に関する規制を、集団規制といいます。原則として都市計画区域および準都市計画区域外においては適用されません。
1つの建築物だけに着目するのではなく、建築物と建築物との関係を規律するのが特徴です。具体的には、下記のような内容の規制です。
①建築物またはその敷地と道路との関係
②建築物の容積率・建ぺい率
③建築物の高さ・敷地・構造に関しての条例
例えば
建築物の敷地の間口は、道路に2m以上接しなければならない、建物の容積率は、都市計画で定められた数値以下でなければならない、などの規制があります。
-
重要事項説明
重要事項説明
- 【読み】
- じゅうようじこうせつめい
- 【意味】
重要事項説明とは、取引主任者が、相手方に取引物件や取引条件などについての重要な事柄を知らせ、相手方が取引をするかどうか決める際の判断材料を提供することです。
この説明は、契約が締結される前に、新たに権利を取得しようとする者(売買における買主、貸借における借主)に対して行わなければなりません。
また、必ず取引主任者が、重要事項説明書を相手方に交付して行わなければなりません。
重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要です。
-
取得時効
取得時効
- 【読み】
- しゅとくじこう
- 【意味】
取得時効とは、一定期間の占有継続により、権利を原始取得する制度です。
原則として、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得します。
ただし、占有開始時に、自己の物であると信じ(善意)、かつ、そう信じたことについて落ち度がなかった(無過失であった)場合には、10年間で時効取得することができます。
また、所有権以外の財産権についても、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に行使すると20年(悪意または善意有過失の場合)、または10年(善意無過失の場合)で、時効取得が認められます。
-
取得費
取得費
- 【読み】
- しゅとくひ
- 【意味】
取得費とは、土地・建物などの取得にかかった金額と、その取得後に生じた設備費・改良費の合計額をいいます。
-
主要構造部
主要構造部
- 【読み】
- しゅようこうぞうぶ
- 【意味】
建物の構造上重要な部分、壁・柱・床・はり・屋根・階段のことをいいます。
-
準工業地域
準工業地域
- 【読み】
- じゅんこうぎょうちいき
- 【意味】
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。
-
準収益
準収益
- 【読み】
- じゅんしゅうえき
- 【意味】
不動産に帰属する適正な収益をいいます。一般に1年を単位として、総収益から総費用を控除して(差し引いて)求められます。
-
準住居地域
準住居地域
- 【読み】
- じゅんじゅうきょちいき
- 【意味】
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。
-
準耐火建築物
準耐火建築物
- 【読み】
- じゅんたいかけんちくぶつ
- 【意味】
準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、①または②のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいいます。
①主要構造部を準耐火構造としたもの
②①に掲げる建築物以外の建築物で、①に掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして、主要構造部の防火の措置、その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
-
準耐火構造
準耐火構造
- 【読み】
- じゅんたいかこうぞう
- 【意味】
耐火構造以外の構造で、耐火構造に準ずる耐火性能で政令に定めるものを有し、かつ国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
-
準都市計画区域
準都市計画区域
- 【読み】
- じゅんとしけいかくくいき
- 【意味】
都道府県は、都市計画区域外に、準都市計画区域を指定することができます。
準都市計画区域とは、都市計画区域に指定するほど規制が必要なところではないものの、相当数の建物が立ち並んできたため、このまま放置すると、無秩序に開発が行われ、住民が利用しにくい状態になってしまうのを防ぐために指定する区域です。
-
準防火地域
準防火地域
- 【読み】
- じゅんぼうかちいき
- 【意味】
準防火地域も防火地域と同じく、市街地における火災の危険を防除する(防ぐ)ために定める地域です。
-
承役地
承役地
- 【読み】
- しょうえきち
- 【意味】
承役地は、地役権が実際に行使されている土地のことであり、「便益を与えている側の土地」のことをいう。民法によると、地役権とは、自己の土地の便益のために、他人の土地を供し得る物権であるとされ、一般に土地がこのような関係にある場合に、自分の土地を「要役地」、他人の土地を「承役地」という。ちなみに、要役地と承役地は、必ずしも隣接していることを要せず。また地役権は、承役地の所有者が変わっても主張できる。
例えば
他人の土地を通行するための「通行地役権」、他人の土地を利用して水を引くための「引水地役権」、眺望を確保するための「観望地役権」などで、これらの地役権を設定・行使されて、実際の便益を与える側の土地が「承役地」となる。
-
商業地域
商業地域
- 【読み】
- しょうぎょうちいき
- 【意味】
商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。
-
使用者責任
使用者責任
- 【読み】
- しようしゃせきにん
- 【意味】
従業員を使って事業を営んでいる者(使用者)は、その従業員が事業を行うにあたって不法行為によって第三者に損害を与えた場合、その第三者に対して損害賠償責任を負います。この責任を使用者責任といいます。
例えばAタクシー会社の従業員としてタクシーの運転手をしているBさんが、業務時間中にCさんを客として乗せて走行中、わき見運転をしたため事故を起こして、Cさんを負傷させたとします。
この場合、運転手Bさんだけでなく、A会社も被害者Cさんに対して損害賠償責任を負います。
従業員の不法行為が外形上業務執行とみられる限り、使用者は責任を負います。
-
譲渡所得税
譲渡所得税
- 【読み】
- じょうとしょとくぜい
- 【意味】
個人の資産、例えば土地や建物、船舶、機械器具などを売って利益が出たら、代金収入のうち、何パーセントかを税金として国に納めなくてはなりません。これを譲渡所得税といいます。
-
譲渡費用
譲渡費用
- 【読み】
- じょうとひよう
- 【意味】
譲渡費用とは、土地・建物などを譲渡するために支出した費用などをいいます。
例えば
立退料や宅地建物取引業者に支払った仲介手数料などがあります。
-
消滅時効
消滅時効
- 【読み】
- しょうめつじこう
- 【意味】
消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。
民法上の一般の債権の消滅時効期間は10年です。債権と所有権以外の財産権の消滅時効期間は20年です。
所有権には、消滅時効はありません。
-
証約手付
証約手付
- 【読み】
- しょうやくてつけ
- 【意味】
手付の一種で、売買契約などが成立したことを証するために交付される手付のこと。
売買契約などが締結されるまでにはいろいろな交渉段階があり、どの時点で契約が成立したのかが一見明確でないことが考えられるので、そのような場合において契約の成立を証明するために交付される手付のことを証約手付という。
-
所有権
所有権
- 【読み】
- しょゆうけん
- 【意味】
所有権とは、物に対する全面的支配権です。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利を持ちます。
「使用」とは使うこと、「収益」とはその物を利用して利益をあげること、「処分」とは売却したりすることです。
例えば
建物所有者は、自らそこに住んだり(使用)、他人に賃貸したり(収益)、売却したり、取り壊したりする(処分)ことができます。
-
審査請求
審査請求
- 【読み】
- しんさせいきゅう
- 【意味】
審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てである。原則として審査請求は処分庁の直近上級行政庁に対して行われる。処分や不作為に直接の関連をもたない行政庁が裁断するので、公平性が高いといわれる。また、第三者機関が審査をすべき行政庁(審査庁)として特に定められている場合もあり、そうした場合には公平中立な裁断が期待できる。
-
信託の登記
信託の登記
- 【読み】
- しんたくのとうき
- 【意味】
信託とは、自己の所有権その他の財産権を他人に移転した上で一定の目的にしたがってその財産の管理や処分をその他人にさせることです。
信託の登記の申請は、この信託による権利の保存、設定、移転または変更の登記(例えば所有権の移転登記や地上権設定の登記)と同一の原因にもとづき、目的不動産が信託財産となったことを公示するために行われます。
例えば
Aさんが自分の不動産をB銀行に信託した場合、その不動産の登記簿には信託の登記がなされ、信託財産となったことが公示されます。この不動産は、受託者(信託される側、この場合はB銀行)に属する財産となりますが、受託者の固有財産ではありませんから、受託者が勝手に処分したり、受託者の債務のために差し押さえたりすることはできません
-
新築
新築
- 【読み】
- しんちく
- 【意味】
新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。
つまり
短期間であっても居住の用に供された場合には、建築後1年未満であっても新築ではありません。
-
新発売
新発売
- 【読み】
- しんはつばい
- 【意味】
新たに造成された宅地、または新築の住宅(造成工事または建築工事完了前のものを含む)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいいます。
また、その申込みを受けるに際して、一定の期間を設ける場合、その期間内における勧誘をいいます。
-
心裡留保
心裡留保
- 【読み】
- しんりりゅうほ
- 【意味】
心裡留保とは、売る気がないのに売ると言ったり、買う気がないのに買うと言うなど、本心ではないことを自分で知っていながら意思表示をすることをいいます。この場合の意思表示が有効となるか無効となるかは、相手の事情により変わってきます。
例えば、Aさんが冗談で「マンションを売る」といい、Bさんが「それを買う」と返事をしたときに、
①BさんがAさんの冗談だということを知らなかったことに落ち度がない場合(善意かつ無過失という)
→Aさんの意思表示は有効
②BさんがAさんの冗談だということを知っていた場合(悪意という)または知らなかったことに落ち度がある(うっかり信じた)場合(善意かつ有過失という)
→Aさんの意思表示は無効
ただし、心裡留保の意思表示が無効である場合でも、売主は善意の第三者(例えば、心裡留保の意思表示の相手方である買主から、さらに買い受けた人)には無効を主張できません。
す
-
筋かい
筋かい
- 【読み】
- すじかい
- 【意味】
筋かいとは、建築物の変形を防止するため、四角形の軸組の対角線に渡す部材をいいます。
せ
-
制限行為能力者制度
制限行為能力者制度
- 【読み】
- せいげんこういのうりょくせいど
- 【意味】
制限行為能力者とは、未成年者や精神上の障害者など、判断能力が十分でないとされる人のことをいいます。
制限行為能力者は、不動産の売買契約などを結ぶときに、それがどのような結果を招くことになるのか、きちんと判断することができないおそれがあります。
そこで、彼らを保護するために定められたのが、制限行為能力者制度です。この制度によって、制限行為能力者が1人でした契約は、原則として、取り消すことができます。
-
正常価格
正常価格
- 【読み】
- せいじょうかかく
- 【意味】
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢のもとで、合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表す適正な価格をいいます。
つまり
不動産の現実の市場価格のことです。
-
成年被後見人
成年被後見人
- 【読み】
- せいねんひこうけいにん
- 【意味】
成年被後見人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所により後見開始(成年被後見人になるということ)の審判を受けた者をいいます。
つまり、精神上の障害で後見人(保護者)が必要だと、家庭裁判所が判断した人のことです。
成年被後見人の保護者を成年後見人といいます。成年後見人は、成年被後見人の法定代理人です。
-
絶対高さ制限
絶対高さ制限
- 【読み】
- ぜったいたかさせいげん
- 【意味】
絶対高さ制限とは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定める高さを超えてはならないとする制限です。
つまり
低層住居専用地域における、日照・通風等良好な住宅地の環境を守るための制限です。
-
接道義務
接道義務
- 【読み】
- せつどうぎむ
- 【意味】
接道義務とは、建築物の敷地は、道路(自動車専用道路、特定高架道路などを除く)に2m以上接しなければならないとする規定です。
建築物の密集している地域を想定して、火災などの消火活動や救出・避難路などを確保するための安全規定です。
-
善意と悪意
善意と悪意
- 【読み】
- ぜんいとあくい
- 【意味】
法律でいう善意と悪意は、私たちが普通の会話のなかで使う意味とは違っています。
一般的に法律でいう善意とは「ある事実を知らない」ということであり、悪意とは「ある事実を知っている」ということです。
善良とか悪質といった、道徳的な意味はありません。
-
専任媒介契約
専任媒介契約
- 【読み】
- せんにんばいかいけいやく
- 【意味】
専任媒介契約とは、一般媒介契約と違い、依頼者が依頼先の宅建業者以外に重ねて売買や交換の媒介、代理を依頼することを許さない契約です。
<媒介契約の種類>
一般媒介 専任媒介 専属専任媒介 他業者への依頼 ○ × × 自己発見取引 ○ ○ × 有効期間 制限なし 3カ月以内(3カ月を超える特約は
無効となり、3カ月に短縮)
更新 制限なし 依頼者の申出があるときに限り更新可 報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上 報告方法 ー 制限なし 指定流通機構への登録 登録義務なし 7日以内 5日以内
-
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約
- 【読み】
- せんぞくせんにんばいかいけいやく
- 【意味】
専属専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。
いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなくなります。それだけ積極的な努力が期待できます。専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。
他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。
-
占有権
占有権
- 【読み】
- せんゆうけん
- 【意味】
占有権とは、自己のためにする意思をもって物を所持することによって成立する権利です。
占有とは、現実に物を持っている、あるいは支配しているという事実状態のことであり、この現実の支配という事実状態を法的に保護しようとするのが占有制度です。
つまり、占有権とは、物を現実に支配している者が法的保護を受ける権利です。
そ
-
総合課税・分離課税
総合課税・分離課税
- 【読み】
- そうごうかぜい・ぶんりかぜい
- 【意味】
所得税は、その所得を10種類に分類し、各所得を他の所得と併せて総合計算するという総合課税を原則としています。総合課税によるのは、利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地建物など以外)、一時所得、雑所得です。
一方、山林所得、退職所得、土地建物などに係る譲渡所得は総合課税ではなく、他の所得と分離して計算する分離課税になります。
-
造作買取請求権
造作買取請求権
- 【読み】
- ぞうさくかいとりせいきゅうけん
- 【意味】
契約期間中、賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の同意を得て建物に取りつけた造作、または賃貸人から買い受けた造作、または賃貸人から買い受けた造作は、建物賃貸借が終了した場合、賃貸人に買い取ってもらうことができます。この賃借人の権利を造作買取請求権といいます。
例えば賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の同意を得て、エアコンを建物に取りつけた場合、建物賃貸借が終了した際には賃貸人に買い取ってもらうことができます。
-
造成宅地防災区域
造成宅地防災区域
- 【読み】
- ぞうせいたくちぼうさいくいき
- 【意味】
造成宅地防災区域とは、宅地造成によって、相当数の居住者などに危害を生ずる災害の発生のおそれが大きい造成宅地の区域で、政令で定める基準に該当するものに指定される区域です。
造成宅地に附帯する(関わる)道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除きます。
都道府県知事が、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて指定することができます。指定された造成宅地の所有者などは、災害防止に努めなければなりません。
-
相続欠格
相続欠格
- 【読み】
- そうぞくけっかく
- 【意味】
相続人が、以下の①~⑤の要件のいずれかにあてはまる場合、法律上、相続人資格を失います。つまり、相続できなくなります。これを相続欠格といい、これによって相続権を失った者を相続欠格者といいます。
①故意に、被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非を弁別する能力がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。
③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
⑤相続に関する被相続人に遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
-
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度
- 【読み】
- そうぞくじせいさんかぜいせいど
- 【意味】
65歳以上の親から20歳以上の子へなされた生前贈与については、その累計額が2,500万円までは控除され、課税されません。累計額が2,500万円を超えた部分につき、一律20%の税率で課税されます。
これにより支払った贈与税を、親の死亡時に贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から差し引くことができるという制度です。
この制度は、贈与税と相続税を一体化して精算するために作られました。ただし、旧来の、生前贈与と相続財産に課税する制度もあるので、納税者はどちらかを選択することができます。
-
相続税
相続税
- 【読み】
- そうぞくぜい
- 【意味】
相続税とは、相続財産を取得した個人に課される国税です。
課税対象は、相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産です。
相続財産から基礎控除を差し引いた額が、課税対象となります。
-
相続人不存在の場合
相続人不存在の場合
- 【読み】
- そうぞくにんふそんざいのばあい
- 【意味】
被相続人が死亡したが、相続人がいないとき、特別縁故者は家庭裁判所に相続財産分与の請求をすることができます。
なお、その請求がなされなかったとき、あるいは請求がなされてもその分与が一部であり、残余財産があるとき、または請求が認められなかったときは、相続財産は国庫に帰属します。
-
相続の放棄
相続の放棄
- 【読み】
- そうぞくのほうき
- 【意味】
相続財産がマイナスの財産(負債)ばかりの場合や、たとえプラスであっても相続人が被相続人の財産を受け継ぎたくないという場合などには、相続人は相続を放棄することができます。
ただし、相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の放棄をしなければなりません。この期間を家庭裁判所において延長してもらわないまま経過してしまうと、単純承認したことになります。
-
双方代理
双方代理
- 【読み】
- そうほうだいり
- 【意味】
双方代理とは、ある者の代理人が相手方の代理人も一人で兼ねること、一人で両当事者の代理人となることです。
本来、契約の両当事者の利害は対立していることから、これを一人の代理人に委ねることは、いずれかの本人の利益を害します。そこで民法は、双方代理を原則として禁止しています。
ただし、
①当事者双方によるあらかじめの許諾がある場合
②債務の履行の場合
には、例外として双方代理を行うことができます。
①は、保護されるべき本人が許諾をするのであれば、それは利益の放棄と捉えることができるためです。
②は、債務の履行は契約において定められたことを行うのみで、そこには新たな利害対立がないことから、本人の利益を害するおそれがないためです。
-
双務契約
双務契約
- 【読み】
- そうむけいやく
- 【意味】
例えば、売主が品物を引き渡す義務を負うのは、買主が代金を支払う義務を負うからだというように、契約の各当事者が互いに対価的な意味を有する債務を負担する契約をいいます。
売買・賃貸借・請負などがこれにあたります。
-
贈与
贈与
- 【読み】
- ぞうよ
- 【意味】
贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で(ただで)財産を与える契約であり、両当事者の合意のみによって成立します。
贈与契約によって、贈与者は受贈者に対して、財産権を移転すべき義務を負います。これに対し、受贈者は何ら義務を負いません。贈与契約は、一方当事者だけが無償で義務を負う、無償・片務契約です。
-
贈与税
贈与税
- 【読み】
- ぞうよぜい
- 【意味】
贈与税は、贈与(死因贈与を除く)により取得した財産を課税対象とする国税です。
納税義務者は、贈与(死因贈与を除く)により財産を取得した個人です。
-
相隣関係
相隣関係
- 【読み】
- そうりんかんけい
- 【意味】
相隣関係とは、隣あわせの土地所有者同士の関係をいいます。その利害関係を調整するために、民法に規定が設けられています。これはもともと所有権に課せられている制約と言えます。
例えば、家から道路に出るには他人の土地を通らなければならない、あるいは、塀の改修工事のために、どうしても隣地の一部を使いたい場合など、隣接する土地の所有者間で、土地の利用を調整する必要があるケースのために、相隣関係の規定は設けられました。
相隣関係には、以下のものがあります。
①隣地使用権
隣との境界付近で建物の建築などをするときは、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができます。ただし、隣地の住家には、隣人の承諾がない限り、立ち入ることはできません。
また、隣地の使用などによって隣人に損害を与えた場合には、償金を支払わなければなりません。
②公道に至るための土地の通行権
公道に面していない土地(袋地)の所有者は、公道に出るため、公道に至るために他人の土地を「必要な範囲で」かつ「他の土地のために最も損害が少ない方法・場所を選んで」通行することができます。
公道に至るために他人の土地を通行することによって、損害を生じさせたときは償金を支払わなければなりません。
③竹木の処理
隣の竹木の枝が境界を越えた場合には、その所有者に切るように請求することができます。
また、隣の竹木の根が境界を越えたときは、排除して(切って)かまいません。
-
促進区域
促進区域
- 【読み】
- そくしんくいき
- 【意味】
促進区域は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として、関係権利者による市街地の計画的な整備または開発を促進する必要があると認められる土地の区域に定められます。
つまり
促進区域は、主として、民間の自主的な地域整備を促すための制度です。
-
組積式構造
組積式構造
- 【読み】
- そせきしきこうぞう
- 【意味】
石、れんが、コンクリートブロックなどをモルタル、コンクリートによって組積して壁体を造る構造です。
-
措置命令
措置命令
- 【読み】
- そちめいれい
- 【意味】
内閣総理大臣は、違反事業者に、その行為の差止め、もしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項、またはこれらの実施に関連する公示、その他必要な事項を命ずることができます。これを措置命令といいます。
不当景品類及び不当表示防止法に違反した事業者への措置として、措置命令が行われます。
-
損害賠償額の予定
損害賠償額の予定
- 【読み】
- そんがいばいしょうがくのよてい
- 【意味】
金銭債権以外の債権が債務不履行となった場合、実際どのくらいの損害額になるか、証明するのが難しい場合も少なくありません。
そこで、債務不履行があった場合に支払うべき賠償額を、あらかじめ特約で定めておくことがあります。これが、損害賠償額の予定です。
例えば
AさんがBさんに建物を売却する契約を締結する際、Aさんが期日に建物を引き渡さなかった場合に、1日当たり1万円の賠償額をBさんに支払うという、損害賠償額の予定を定める場合があります。
-
損害賠償額の予定としての手付
損害賠償額の予定としての手付
- 【読み】
- そんがいばいしょうがくのよていとしてのてつけ
- 【意味】
契約違反があった場合、実際の損害額にかかわらず損害賠償の予定額として没収するという趣旨で交付される手付。この手付が交付された場合、実際の損害額が手付額を超えることが判明しても、超過額について損害賠償請求できない。